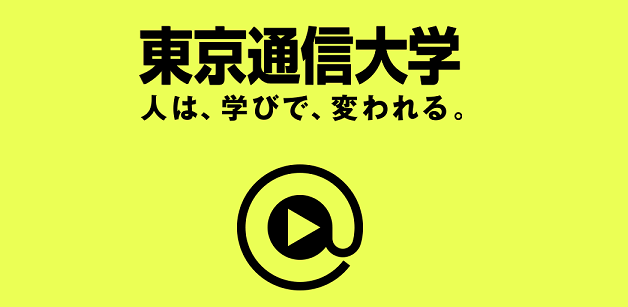本記事では、東京通信大学の授業を受けるにあたって、重要なヒントや、ものすごく使えるフリーソフトの紹介や、ウエブサービスへのリンク、教材の不具合の回避の仕方など盛りだくさんですので、下の方までよく読んでいただけると幸いです。
こちらも超参考記事
概要
東京通信大学は、通学無しで学士の資格を取得できる通信制の大学です。他の大学に比べると卒業までに必要な費用が安かったり、単位習得に本当に一切のスクーリングの必要がない(つまり世界中どこででも自分の時間配分で受講できる)などのメリットがあり、社会人にも人気があるようです。実際私も授業の大部分を居住先の外国でうけています。
また、1つの単位は8回に分かれた「授業」があり、1授業回の中には4つにわかれた15分~20分程度の動画講義があり、各回の終わりにオンラインで受ける「小テスト」、全8回の授業の終わり(学期末)に、これもオンラインで受ける「単位認定試験」があります。学期は1年に4回あります。つまり約3ヶ月サイクルで学期が進んでいくわけです。
実際の授業は・・・
小テストの他にも課題があったり
科目によっては、小テストの他に、課題としてファイルを作成したり、レポートを提出したりするものや、ディスカッションボードという掲示板に自分の意見を1回投稿し、他人の投稿に最低1回コメントするといった課題を出している科目もあります。
プログラミングの課題があったり
プログラミングの演習科目では、実際にWEBブラウザ上でプログラムを組んで実行できるオンライン開発環境「@code room」が用意されており、これを使ってjavaやC言語の勉強を行います。

授業資料がスッカスカの授業や・・・
一番困るのが、動画のほうではバンバン資料や表や説明が出てくるのに、配布されている授業資料にはほとんどなんにも書かれていないような科目。
「学業は自分なりのノートをとってなんぼだ!」などと旧態依然とした昭和脳の教授先生もいらっしゃるわけです。こういう地雷科目は、履修しないのがいちばんですが、こういうのにかぎって必須科目だったりします(泣)。
個別の教員に質問を送った場合は、単純に答えを教えるだけでなく、ほんとうに親身になって理解を深められるようにアドバイスしてくれたりします。
ですので、履修登録時に地雷科目を回避して、あとはまじめに受講していけば、酷くない大学ライフを送れます。
授業資料に書いてある言い回しと全く違う単語をテストに出す科目や・・・
地味にめんどくさいのが、授業動画や授業資料で使っていた言葉や単語を試験になると変えて出題する科目があること。テストに出ている単語を授業資料などで検索をかけてもぜんぜんひっかからない。これも、授業動画を鬼のように何度も見てしっかりメモをとって、内容をよく理解しないと突破が難しい(つまり履修を完了するのにに多大な時間がかかる)地雷科目と言えるかもしれませんが、逆に考えると、それだけ授業を熱心に受けることに繋がるので・・・結果的にこれもしんどいけどためになる授業と言えるかもしれません。
※しかも動画にすら出てこないことをテストで出題したりする困った授業もあります💦
ビックリするくらい棒読みの授業や・・・
これもたまにありますが、とにかく棒読み丸出しの授業。そして資料を読んでいるだけで何の追加知識もない。こんなんならアナウンサーを雇うか、Text2Speechのコンピュータ音声でも良いくらいな・・・いや、資料読んでるだけなら資料配って「読んどけ」でもう十分(笑)でも授業の内容自体はちゃんとしているので、棒読みの授業を何時間も聞かされて睡魔がはんぱなく襲ってくるのをなんとか濃いコーヒーでも淹れて凌ぐしかない・・・💦
授業資料が超神がかり的にすべて網羅されている授業など・・・
地雷科目があったかと思えば、授業資料のPDFだけで小テストなどはラクラク突破できてしまう。言い換えれば授業動画はながら見程度で済んでしまう神科目もいくつか存在しています。ネットでの先輩のブログなどをよく見て、神授業を探して履修すれば、非常に楽に単位を取れます💦
良くも悪くも大学は自分次第(GPAという難題)
このようにいろいろなセンセイがたが授業をしてくれるわけですが、まず「履修科目を適当に選ばない」ということと、「あれもこれもと自分が使える時間を考えないで履修登録しない」「履修したからにはとことんつきあう」ということが重要ですね。
昔の大学では、履修はいっぱいしておいて、つまらないとか自分にあっていないと思った授業は見捨てて取り組みやすい科目の単位を取って、最終的に卒業に必要な単位が取れればOKのような傾向もありましたが、最近では「GPA」という評価基準があるので、あんまり捨て科目を量産すると、卒業要件は満たしていても、成績の評価がダダ下がりになり、いろいろ不都合が出たりします。アメリカの会社への就職ではこのGPAをもとに評価されたりもするそうです。
そしてまずは履修登録!
大学というところは、教授の性格の良し悪しで楽しい学生生活がおくれるか、苦しい学生生活になるか決まってしまうと言っても過言ではないです。ですので、科目を履修する際には、インターネットで「東京通信大学 神授業」などで検索して、地雷科目をふんずけないように履修登録することを強くおすすめします。まあ、必須科目ならしかたないですが(笑)
履修に関するヒント
前述したとおり、TOUの科目は1回に4つの動画授業を見て最後に小テストを行うということを8回やって最後に単位認定試験を受けるのが定石です。この「1回に4つの動画授業を見て」という部分では、平均して1回15分くらいの動画を4回=60分。「小テスト」では見直しや100%にするために再試験したりPDF資料などを整理する時間がかかりますので、いろいろ総合すると、1回の授業に約2時間程度みておくと良いとおもいます。
1回の授業だけを考えれば良い理由
TOUの動画授業は、いっぺんに全8回分公開されるわけではなく、2週間くらいごとに1回目と2回目、3回目と4回目のように徐々に公開されていくので、全授業の履修に必要な総時間(約25時間)を考慮するよりも、これから履修登録する授業が1回に3時間かかるということを考えて履修すると良いと思います。10科目履修するとすれば、1回の授業を小テストまですべて完了するのに理論値で3時間かかると考えると10科目で30時間勉強にあてる必要があるということがわかると思います。
- 週7日勉強すると・・・・1日4.3時間
- 月~金で勉強すると・・・1日6.0時間
- 土日だけ勉強すると・・・1日15時間
上記のような感じでスケジュールをたてなければならないことがわかります。実際はスパッとできてしまう神授業や自分の興味のある授業などはもっと短時間でできてしまいますが、1回3時間ルールで履修のスケジュールをたてておくと時間的に追い詰められずに済むと思います。
聞き流せる授業と聞き流せない授業がある
講師によってはPDF資料が秀逸すぎて動画授業をあまりよく見ていなくても楽勝で試験を突破できる科目も多数存在しますが、それだけで卒業できるほど甘くはありません💦
PDF資料がド貧弱だったり、動画を何度も見ないと(あるいは講師に質問を送らないと)理解できないような授業も多々あるので、自分でノートを作っておく必要のある授業も多数存在します。こういう授業は通勤中に電車の中でスマホで見て終了とはならないので、要注意です。
ぶっ通しの履修はやらないほうが良い
1日の休みもなくぶっ通しで履修しないと単位を取れないような履修登録は絶対にお勧めできません。生活していればなにが起こるかわからないので、履修登録を完了する前に、その期に予定しているイベントや約束をできるだけすべて並べてみて、どれくらいの科目を履修するのが良いのかじっくり考えるべきです。
かといって何も履修しない期をつくったりして、後になって卒業単位がたりないからといっぺんに20科目も履修するようなことは避けたほうが良いです。忙しいと余禄できる期は「神授業」と呼ばれているような単位認定試験が無い科目や、課題をやれば良いだけの科目を3つか4つ選んで履修すると良いと思います。
ちなみに筆者が1度に履修した最高科目数は16です。死ぬかと思いました(笑)
2単位4単位もらえる授業がある
4年生の「指定演習」という授業は2学期間を使って2単位とれる授業です。選択必修なのでいくつかあある指定演習の科目から1つはかならず履修しなければなりません。かなり難易度が高いのであまりお得ではないのですが、このなかに「実践ゼミ」といって実践ゼミAで2単位、実践ゼミBで4単位!とれる科目があります。筆者は受けた事が無いですが、これはかなりオイシイですね・・・。
ちなみに日本国憲法という科目も2単位取れますが、これは1つの履修期間が通常8回の授業のところ、16回分あるという忙しい授業になります。ただ、履修した人の話しでは、履修する価値はあるそうです。
授業に関するヒント
今も昔も参考文献などは読んどいたほうが良い・・・
シラバスで参考文献としてあがっている書籍は、一応目を通しておいたほうが良いようです。科目によっては、とある新書をベースに授業展開するものもあり、試験などもその参考書から出る場合があるので、そんな本を読んでいると、成績にも差が出ます。新書などは高くもないので、買っておくと良いと思います・・・。
授業で使用している本は、可能な限りAmazonのkindleで購入することをおすすめします。理由は、kindleであれば「検索」ができる点。とつぜん調べたいものがあったりしたときには絶大な便利さを発揮します。
受講に関するヒント・・・
前述の通り、授業の配布資料のPDFにマーカーを入れたり、書き込みをすることは非常に重要になってきます。ですので、PDFを編集できるソフトや、iPadなどで手書きでPDFの上から書き込みができるようなソフトなど、自分なりの工夫が重要です。また、配布資料は基本的に鍵がかかっていて内容を変更することはできませんし、コピペもできなくなっています。

ただしKindleの検索機能はしょっちゅうバグります。試験中にkindleが動かなくなったりクラッシュしたりしたときのために、スマホやタブレットなど代替手段を用意しておいたほうが無難です。
課題に関するヒント
Chat GPTやネット掲載情報をコピペすると大変なことに
プログラミングやレポートの課題をネットから拾ってきたり、Chat GPTの出力をそのまま使うと、数百人から数千人いる生徒の多くが似通ったものを提出することになります。また、最近は教師用の盗作防止ソフトも性能があがってきているので、同じコメント、同じ変数名、同じ関数名、同じ論旨、類似の文などに気をつけていても、だいたいバレるみたいです。無断コピペ、盗用、剽窃(ひょうせつ)は、大学では重罪です。下手をすればそこで終わります。絶対にAiやネットから拾ってきたものをそのまま貼るのは止めましょう。
Chat GPTやネット掲載情報はうまく使いこなす
ネットの情報をそのまま提出するのはだめですが、課題作成の参考にしたり、論文で正式な手順で引用することが許可されている科目ならOKだと思います。プログラミングの課題は、全てを100点にするというよりは、構造を理解していないと単位認定試験を突破できないので、どんどん質問フォームを活用するべきだと思います。事細かく教えてもらえますので、そういうものを利用すべきでしょう。
テスト突破のヒント
最重要情報
TOUの試験はすべてオンラインで行われるので、予期しないトラブルも発生します。たとえば試験中にPCが突然フリーズしてしまったり、ネットワークが切れてしまうといったトラブルは普通に起きます。小テスト中や、単位認定試験中に有名な突然再起動してしまういわゆる「KP41病」が起こってしまったらと思うと不安ですよね・・・。
そんな突発事象が起こってしまったら、やるべきことがあります。
試験中にトラブルを申告する
試験中にトラブルが起こった際には、まずなによりも大事なのは、「必ず試験期間中に」@campusの「キャンパス・サポート・センター」に連絡することです。連絡先は以下に示します。

問合せ種別は「システムについて」、利用端末、OSバージョンとブラウザはご利用中のものを書きます。そして問い合わせ内容には、状況説明を書きます。
ここでTOUのシステムに文句をつけてもはじまらないので、辛辣なクレームや罵詈雑言を書くのはやめておいたほうが良いですよ
小テスト突破のヒント①・・・小テストは全部正解にする
小テストの結果は、単位取得のための評価条件に入っています。そして小テストは3回まで受けられます。ですので、小テストで1つでも間違いがあったら、すべて正解するまで受験しなおしたほうが良いです。3回目を終えるか、もうこれ以上受験しないと選択すると、各質問の詳細な解説を見ることができるようになります。科目の認定条件の多くは小テストが50%、単位認定試験が50%で採点されますから、小テストがすべて100%なら単位認定が相当楽になりますよね。
小テストのヒント②・・・小テストは全部記録する
学期末の単位認定試験では、小テストそのものの問題が出ることは少ないですが(科目によってっは単位認定試験の半分以上が小テストから出るものもあります)、問題が似ていたり、選択肢が似ている問題が出ることがあるのと、もしも小テスト中に間違えた箇所があった場合、合計3回までは再テストできます。そして再テストでは、既出の問題が再度出る確立が非常に高いので、すべての問題の問題文と答えと出典箇所(10問答えて結果がわかったあとで問題を再度見ると下の方に出題範囲が表示されている)を控えておくようにすると、2回目以降の回答時間が短くできます。ですので、すべての授業回のすべての設問と答えを1つのWordファイルなどに記録して、最後に全体を横断的に検索できるようにしておくと、便利です。
ただし!これには注意!
まあ誰とは言いませんが、筆者が「糞」認定させてもらっている科目の講師は、動画でも言及していなく、PDFもド貧弱で、しかも自分の勝手な意見を試験の正解とするようなアホな問題をだすヤカラがいます。自分の経験とか勝手な意見を問題に出されたら、一般論ではぜったいに答えられないので、これは答えようがありません。こういう講師の試験でSを取るのはまず無理なのでムキになって小テストで100%を取ろうとしなくて良いと思います。A狙いで良く、わけのわからない問題は1つくらいは無視で良いと思います。
小テストは問題をコピペ・選択肢ならスクリーンショット
問題の文をコピペでワードに貼り付け、答えはスクショでワードなどに記録していきます。もしも余力があれば、回答も手打ちで文字にしておくと、単位認定試験のときに検索できて便利です。
特に計算が絡んでくる問題は、完全に理解できるように付加情報があればどんどん記入しておいたほうが良いです。
穴埋め問題では配布資料からコピペしないほうが良い
特に単位認定試験では要注意。問題の空欄をキーボードからの入力で記述する「穴埋め」問題。これにはとんでもない不具合が潜んでいます。ほんとうに極ごくたまにですが、配布資料のPDFで使われている漢字コードがおかしなことになっていることがあり(もしかすると講師の罠かも説もあります💦)、PDF資料から単語をコピペして穴埋め問題の空欄に文字を入れると、この間違った文字コードのせいで、見た目上は正しい単語を入力しているのに正解と認識されないことがあるという問題。
これは、PDF資料の文言をコピペで解答欄に入れるのではなく、一度秀丸や寺パッドなどのテキストエディタにペーストして、正確な文字になっているか確かめたものを使うか、シンプルに直接キーボードから入力するようにすれば問題が起こりません。
かならず準備してから試験を開始すること
単位認定試験も小テストの場合でも同じなのですが、授業資料にマーカーや書き込みを多く入れておいて、いざテストのときに開こうとすると、アクロバットが落ちて閲覧できないことがあります。こんなことにならないように、テストを始める前に、必要な資料はすべて開いて、ページをスクロールできるか、検索できるか、後ろに人がいないか、すべて準備ができてからテスト開始のボタンを押すようにしましょう。後ろに人が映り込んだり、PDF閲覧ソフトがクラッシュしてしまって閲覧できない状態になったら、トラブルシューティングの章を御覧ください。
学習環境のトラブルシューティング
語学教材の文章が見えないことがあるトラブル
下記の画像⇩のように、語学教材(有料)をやっていると、たまに「クリックして話す」などのガイドが、英語の文章の上に被ってしまい、見えなくなってしまうというションボリ仕様💦。ほんとうにイライラしますが、これを一時的にですが回避する方法があります。

この下の写真⇩のように、右下にある解像度変更のリンクをクリックすることで、邪魔なガイドを一時的に消すことができます。これで語句をよく覚えたら、中央のマイクのボタンを押して発声するわけですが、マイクのアイコンをクリックすると、また邪魔なガイドが表示されて、語句を見えなくするので、声をだす前に、もう一度、解像度変更のリンクをクリックしてガイドを消してから発声するようにすると、怒りとイライラのフラストレーションでパソコンの画面を叩き壊すこともなくなります(笑)。ちなみに筆者はモノにはあたらない性格なので、捨て台詞を吐く(ストレス小の時)か、激辛カレーを食べる(ストレス中の時)か、和菓子を食べる(ストレスMAXの時)かしてフラストレーションを解消しています(爆笑)

PDFが落ちて見れない時の回避方法
テストを開始してしまってからPDFが見れない状態になっていることに気づいてしまっても、慌てず騒がす、エクスプローラーからWEBブラウザへPDFをドラッグ&ドロップすると、WEB版のビューワーでファイルを見ることができたりします。
特に全8回分のPDFを全部つなげると結構おおきなファイルになるので、落ちたりすることもまあまあ頻繁に起こりますので、対策方法をしっかりと熟知しておくのが良いと思います。
余談ですが、WindowsのパソコンでPDFがクラッシュするのであれば、iPadなどWindowsではないデバイスでファイルを開いてみると見れる場合があります。いずれにしましても、不測の事態を避けるために、まず、試験を始める前に、予めすべての見るかもしれないファイルは開いておくということを徹底しましょう。
アクロバットが遅すぎる場合にする設定変更
プログラミング演習環境のヒント
@code roomのヒント
東京通信大学でプログラミング演習を行う際に使う公式な開発環境は「@code room」です。この@code roomでプログラムの開発を行う場合、「プログラムを編集 ⇨ コンパイルタブを開いてプログラムをコンパイル ⇨ 実行タブを開いてプログラムを実行」 という流れでプログラムを試すことができますが、編集したプログラムは「保存」をしないと最新のプログラムをコンパイルできません。どこにも書かれていませんが、ここで便利なのが「CtrlキーとSキー」を同時に押すとプログラムの保存ができるという豆知識。これは地味に便利です。
@code roomの要注意ポイント!
これを知らないであわてふためく不注意者が毎年出るようです。挙句の果てには授業で使う掲示板に苦情を書き込むアホなヤカラまで現れる始末(最初からわかっていることなので掲示板に文句を書いたって無駄だし、そんなことをしたって1000人近いクラスメートから失笑されるだけですし、「自分は注意書きも読まないアホの不注意者です」と公言しているのと同じなので、止めましょう)。まず、@code roomが使用できなくなる期間をしっかりと確かめておくべきですが、それでもコードを実行して試したい場合は、下記で説明している「paiza.io」などの代替えのプラットフォームを用意しておくと便利です。
@code roomの要注意ポイント2
@code roomで開発したコードやSQL文は、パソコンのフォルダにエクスポートして取っておいたほうが良いです。単位認定試験などで類似の問題が出ることがあります。
試験中でも使えるオンラインSQLite環境「SQL Fiddle」
SQLiteがブラウザだけで使えるだけでなく、ちゃんとトランザクションも正常に処理できる環境です。SQLiteだけでなく、MySQLやPostgleSQL、MariaDBなどもオンラインで利用できます。そしてこのSQL Fiddleは、SQL関連の質問用にカスタマイズされたChatGPTが使えてしまいます。SQLに関してわからないことはここでチャット形式で質問すればかなり正確に答えがわかります。
ChatGPTで生成した文章やプログラムソースには非常に顕著な特徴がありますので、見る人が見ればすぐに分かってしまいます。ChatGPTの出力をそのままコピペして提出すると、単位取り消しや退学処分などのペナルティを受けることがありますので、答えの丸写しは止めましょう。
試験期間中でも使えるオンライン・プログラミング環境「paiza.io」
プログラミングの演習科目は、数回の授業に1度(4回目と8回目の授業回など)、評価の対象となるプログラミングの課題が出されます。また、小テストや単位認定試験中は、オンラインの開発環境「@ Code Room」は使えなくなります。そこで、同じようなオンラインの開発環境を無料で提供しているサービスを知っていると、なにかと便利です。「paiza.io」というサービスは、javaだけでなくC言語やpythonなど複数の言語をサポートしていて便利です。下記のロゴをクリックするとオンラン実行環境のページを開きます。

まだまだあるオンライン実行環境
| JDoodle | Java以外の言語にも対応している。 |
| Replit | プロジェクト管理や共同作業も可能 |
| OnlineGDB | デバッガ機能が付いている |
| Ideone | プログラムを保存・共有できる |
| Coding Rooms | 教師や生徒のためのリアルタイム共同作業機能 |
教科書を見る際のヒント
1つの授業が4つの動画と1つの小テストで構成されていることはお話しましたが、これを全部で8回受講し終えると、最終的に学期末の単位認定試験へとすすみます。これを突破するにはいくつか考慮しておくべきポイントがあります。
授業資料のPDFをすべて連結!
授業で使ってきた配布資料のPDFファイルは、すでに自分の書き込みやマーカーなども入り、授業の内容を網羅しているので、単位認定試験では一番利用する材料の1つになっていると思います。
そこで、全8回の授業で使ったPDFをすべて連結して、1つのPDFファイルとしておくことで、すべての資料を横断的に検索できるようになり、試験中に見るのに非常に便利です。PDFを連結するのはオンラインのサービスでもいろいろあるので各自しらべてみてください。筆者はいろいろな機能が豊富な下記のオンラインサービスを使っています。

タブレット+ペンで授業ノート作成

最近の若い学生はiPadなどのタブレットと専用のペンを組み合わせて授業ノートを手書きで作っている人も多いそうです。手書きで書いてもテキストとして保存できたり、手書きの図形などを検索したりもできそうなので、時間があったら環境を作ってみたいと思っています・・・💦
論文の書き方神サイト
大学では論文形式の文書の提出を求められることも多くなります。TOUでもアカデミックライティングという授業がある。これはレポートの書き方の指南のような内容なので受講しておくと良いです。そしてここに紹介する神サイトは、論文の書き方を非常にわかりやすく「桃太郎」の物語を論文形式にしながら説明してくれています。
とかく論文の書き方などを解説しているブログやウェブコンテンツを見ると、サンプルとして書かれている例文の内容がややこしすぎて、あたまに入りずらいことがありますが、このサイトでは話の筋が誰でも知っている物語なので、理解しやすいです。
そして、論文の完成形が非常にコンパクトにまとめられている「サンプル論文」の全文が紹介されていますので、それを見るだけでもかなりイメージができるとおもいます。
その他の便利なリンク集
筆者が受講に際して利用しているサイトのリンクを集めてみました。
- 基本情報技術者試験ドットコム
実際に基本情報技術者の試験問題を取り扱う授業があります。 - ITパスポート過去問道場
ここの過去問からの出題のある授業もあります。 - 論文検索(サイニー)
学術論文などの書誌情報の検索などに。 - 国立国会図書館
日本で発行されたあらゆる書物が収蔵されており閲覧できます。 - グーグルスカラー
同様に学術文献などの検索に利用できます。 - I LOVE PDF
PDFファイルの結合などをオンラインで行えるサービス。 - PlantUML Web
ソフトウエア工学の授業などで使用するUMLの描画ツールWEB版
技術系の授業に便利なサイト
- プログラム・オンライン実行環境(paiza.io)
WEB上でJavaやC言語のプログラムを編集して実行できる環境です。
TOUの開発環境は試験期間中になると利用できなくなるので、こちらが便利。 - いろいろな計算ができる超便利サイト「算数の電卓」
分数関係のいろいろな計算でほんとにお世話になっています。 - IPアドレス範囲の計算機
サブネットマスクを入力して最初と最後のアドレスを計算してくれるツール。
「インターネット技術A」などの講義の受講に便利。
中国語の授業に便利なサイト
- 中国語の発音解説サイト
中国語の授業で行う母音や子音の発音を解説して実際の発声もサンプルとして挙げているサイト。 - 中国語お名前チェッカー
日本語の名前を中国語に翻訳できるサイト。 - Weblio
漢字の中国語を入力すると発音を再生してくれるサイト。
関連性のある本サイトの記事
paiza.ioのヒント
R言語とR Studio Desktopのインストール方法解説
その他の便利ソフト&フリーウエア
画像ファイルをJPG画像に一括変換

指定したフォルダ以下の全サブフォルダを検索し、見つけたPNG画像などの画像ファイルを一括でJPGファイルに変換するフリーウエアを自作しました。これは使える。というか、わかる人には絶対にわかるTOUのオンライン授業を受講するのにほぼ必須といっても良いようなツール。Vectorのフリーウエアに登録中。
WEBページをまるごとスクリーンショット

ブラウザのプラグイン「Go Full Page Screen Capture」これをWEBブラウザに仕込んでおくと、ほしいページの先頭から末尾までをまるごとPNGファイルにしてくれる。
更に便利なライフハック
PDF資料が薄すぎる授業の対策
PDF資料に動画で話している内容がぜんぜん書いてない授業も多いです。そんなときは、iPhoneのディクテーション「音声入力」機能を利用すると便利。ただし、Aiを使ったディクテーションはまだ完璧ではないため、音声入力したテキストをもう一度授業動画を見直しながら修正しなければいけないが・・・。授業動画を2回づつ見れば、かなりの部分覚えてしまって、テストが楽になるという副作用があります(笑)

国立国会図書館の利用者カードを作っておこう

せっかく大学生になるわけなので、大学っぽいことをやりましょう。国立国会図書館 の利用者カードを作って実際に中に入ってみましょう。東京本館は、国会議事堂の近く、憲政会館の向かい側にあります。初めての人は、新館の入口から入ると、入ってすぐのところにスタッフさんが立っているので、その人に聞くか、新館を入ってすぐ右側にあるカウンターで、利用者カードを作りたい旨を伝えて下さい。身分証明書が必要です。待っている人が少なければ、すぐ作ってくれます。国立国会図書館は入退館、本の検索・貸出・複写・返却の全部と手続きがこのカードでできます。